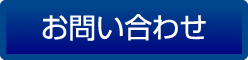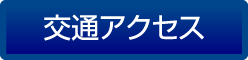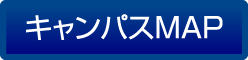ベストティーチャー賞(令和4年度)
ベストティーチャー最優秀賞
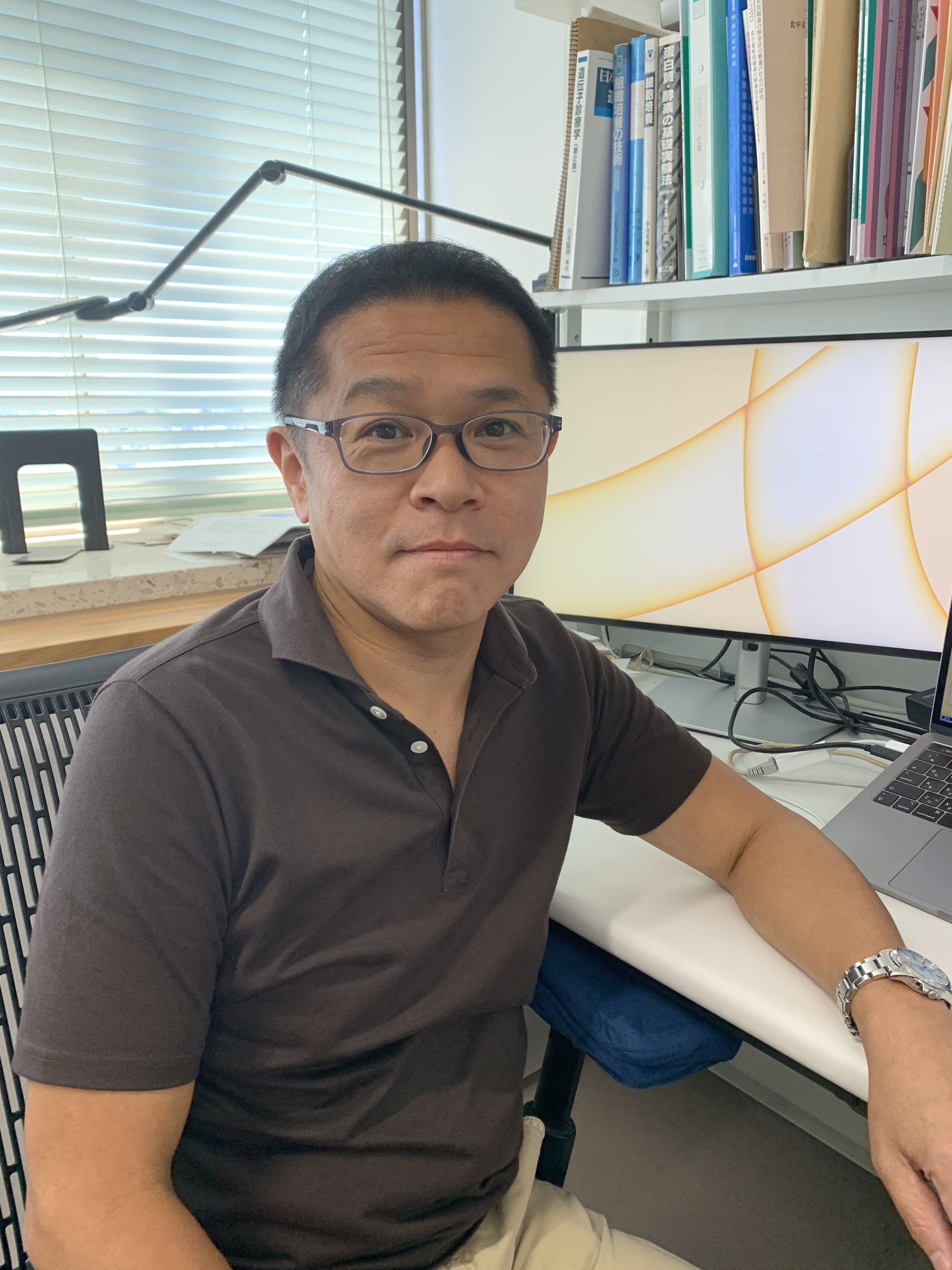 |
氏名:大岡 唯祐 |
この度は、令和4年度の医学科最優秀ベストティーチャー賞に選んでいただきましたこと、大変光栄に思います。
私が主に担当しているのは医学科2年次の「微生物学」の講義・実習です。「微生物学」は3年次に学習する「感染症」とは異なり、”感染症”の原因となる”微生物”をより深く理解し、「感染症」を学ぶ前に”病原微生物を正しく恐れる”ことが出来るようになる事を目的としています。ただ、微生物は基本的に”目に見えないもの”なので、学生にイメージを持たせる工夫が必要です。そのため、講義・実習では以下のような工夫をしています。
【講義での工夫】
講義前:視覚的に記憶に残るよう図表や写真を多く使って作成した「要点のレジュメ」や「病原機構や臨床症状のスライド」を事前に公開し、学生が積極的に予習出来る環境作りをしています。
講義時:事前に公開した資料を示しつつ、より細かな説明を追記していき、学生自身が付帯情報を資料に書き込むことでアクティブ・ラーニングを促しています。また、項目毎に問題を提示し、理解度の確認を行っています。
講義後:webアンケートを利用し、学習した点や質問を学生に記入してもらい、全員からの質問とそれに対する回答をQ&Aとして公開し、学生全員が共有出来る環境を作っています。このアンケートは、直接質問に来ることに躊躇しがちな学生の持つ疑問の解消にも繋がっていると考えています。また、「講義内容が難しかった」という指摘があった場合は、必要に応じて資料を追加し、次の講義で補足説明しています。
【実習での工夫】
実習前に、実習の目的や原理を理解できる資料を作成・配付し、実習時の説明にも利用しています。医学科の実習は120人と多く、実習手技の個別指導が困難なため、各実習項目について、使用器具や作業工程および細かな注意点を付した動画を作成し、作業前にスクリーンに映しながら説明しています。また、作業中も映像を流し続け、随時手技を確認できるようにするとともに、時間があるときは常に学生の中に入って質問しやすい環境を作っています。
話は変わりますが、医学部は医師国家資格取得のために学習することを目的とした学部であり、他学部のように卒業論文で学生が配置されることはないため、基礎講座で研究を行う学生をリクルートするのが非常に難しいのが現状です。私は「微生物学」の講義・実習は、学生に知識を伝える場であるとともに、研究の楽しさをアピール出来る場であると考えています。そのため、実際の講義・実習では、授業内容から脱線して雑談(全く違う話や研究の話)をし、実習中に学生の中を回って話しかけることで、質問に限らず、学生が教員に接しやすい環境作りを心掛けています。その効果もあって、現在、2年次「微生物学」の講義・実習を通して、微生物学の基礎研究に興味を持ってくれた学生3名(現、5年生)が選択科目の自主研究を選択し、研究を一緒に進めてくれています。
最後に、今後も講義・実習をアップグレードしつつ、学生とともに楽しく教育・研究をすすめて参りたいと思います。
ベストティーチャー賞
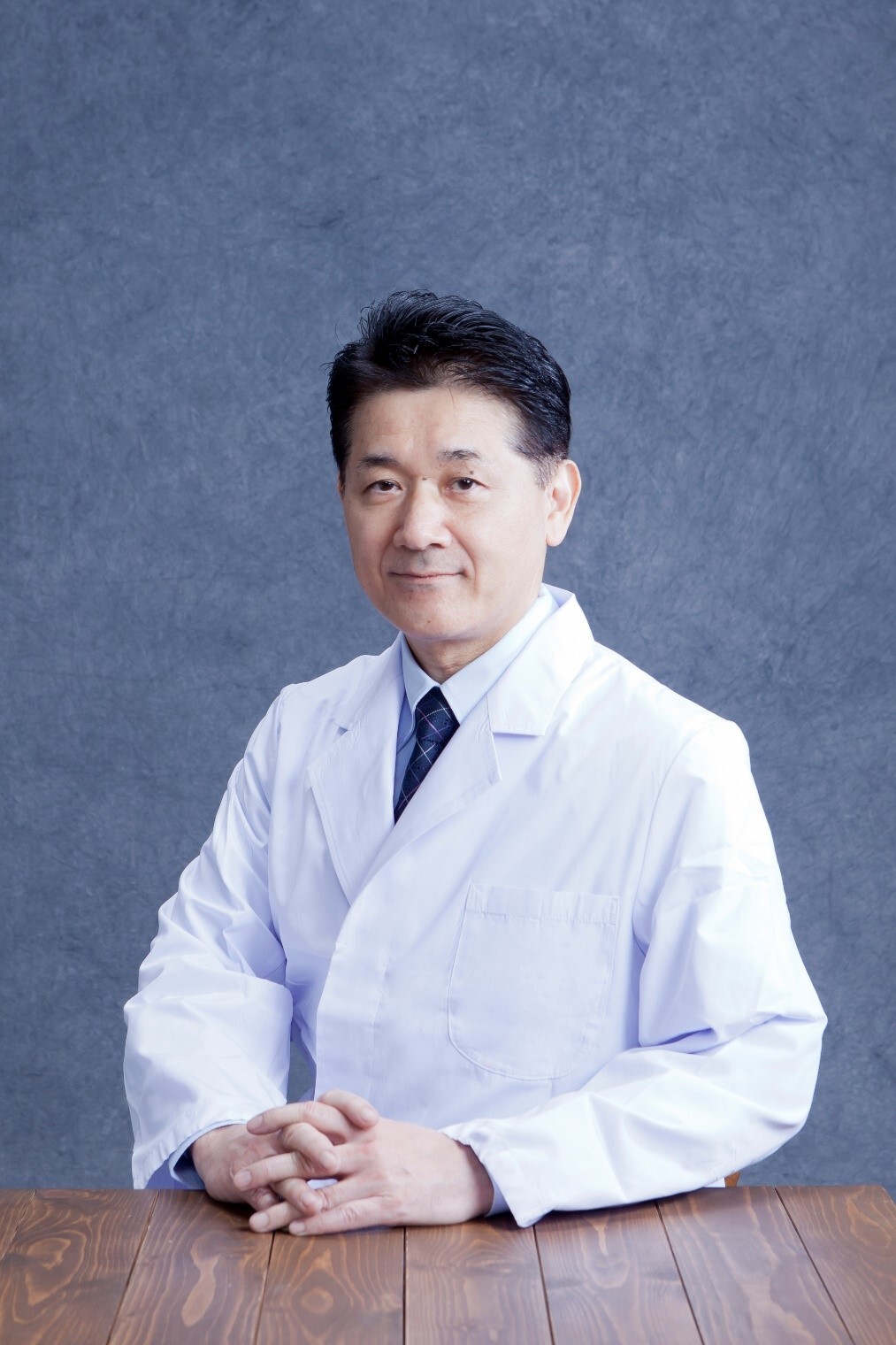 |
氏名:垣花 泰之 |
この度、令和4年度鹿児島大学医学部医学科ベストティーチャー賞に選ばれましたことを大変光栄に存じます。
私は鹿児島大学医学部医学科を卒業後、麻酔・蘇生学教室に入局しました。その後、集中治療室で勤務する機会があり、集中治療医学の面白さと奥深さに魅了されたものの一人です。「なぜ集中治療医学は面白いのか」を考えた時、私の場合、多臓器不全の病態探求から身体の神秘を感じそれに驚かされ、その不思議さを追求したいと強く感じたからなのだと思います。学生講義においてそのことをできるだけ学生に伝えたいと思っています。多臓器不全の概念は1940年代以前にはありませんでした。一つの臓器が機能不全になると、それは死を意味していました。しかし、1940年代から50年代にかけて人工呼吸器や透析装置が開発されたことにより、重篤な呼吸不全や腎不全でも生命を維持できるようになりました。その一方で、多臓器不全という新たな病態が生み出されてきたのです。多臓器不全の病態を解明するには、臓器別に発展してきたこれまでの医学体系を超えた新しい臓器横断的な学問体系が必要でした。我々の体は、単なる臓器の集合体ではありません。各臓器がネットワークを作っており、それが破綻した状態が多臓器不全です。そのような重症な患者さんを救命し社会に返してあげるための医学・医療を学ぶことが、生命の成り立ちを学ぶことにつながるのだと感じた私は、集中治療医学にのめり込んでいきました。その中で学んだことは、「すべての病態には必ずそれなりの理由(わけ)があり、長い進化の過程で我々の体(細胞・臓器)が獲得した生命を維持するためのとてつもなく精巧なシステムが存在する」ということでした。さらに、「病態は宿主の状態や時間軸により大きく変化し治療戦略も変わっていく」ということも学びました。そのため、病態を正確に評価し現在の治療戦略が正しいのかを常に考える思考回路を持つことが重要であり、データだけに頼るのではなく、直接しかも詳細に患者さんを診察し判断する必要があります。私は、これまでの臨床経験を通して多くのことを患者さんから学びました。そのことを学生の皆さんに還元したいと考えています。生命の神秘とその不思議さを、基礎と臨床を結びつけながら、できるだけ実臨床の体験談を話すようにしています。医学教育モデル・コア・カリキュラムにおいては、科学的探究心をもって日常診療に取り組む臨床医の養成、研究者育成の視点の重要性を掲げています。医学生は、「これまで学んできた基礎の知識が臨床の疾患や病態とどのように関連するのか、進化の過程で獲得した様々なシステムがどれだけ複雑で綿密に仕組まれたものなのか、臓器はお互いにネットワークを形成し臓器連関により信じられないほど精巧な機能をどのように発揮しているのか」を知った時、身体の神秘に魅了され、医学・医療の面白さと素晴らしさを理解し、学習意欲も高まり、科学的探究心にもつながるのだと思います。そのことを学生に伝えたいと思っています。それが私の授業に対する心がけです。
 |
氏名:中畑 新吾 |
この度は、医学科ベストティーチャー賞を頂き、大変光栄に思います。私が所属するヒトレトロウイルス学共同研究センターは、もともと医学部附属の難治性ウイルス疾患研究センターとしてスタートしました。医学部生との関わりもあり、教育では医学科4年生の必修科目である「自主研究」を担当しています。医学部の学生にとって初めての研究室配属となる「自主研究」のカリキュラムは、リサーチマインドの養成に貢献します。私は、この教育プログラムを通じて、実験の技術や知識を伝えることよりも、研究の本質を実際に経験し、理解してもらうよう努めています。基礎科目の実習は、与えられた方法で予測通りの結果が得られる題材が使用されることが多いことから、研究の本質やその楽しさを理解するのは難しいと感じます。「自主研究」では、すべての学生に研究の世界に一歩足を踏み入れてもらう貴重な機会を提供できると考えています。
「自主研究」では、約2ヶ月間、配属された研究室で実験を行いますが、当教室の「自主研究」では、研究テーマを与えるだけでなく、学生自身が積極的に研究テーマを探求する機会も提供しています。たとえば、データベースから興味を持つ遺伝子を選んでもらい、それを基に研究テーマを検討するよう促す取り組みを行っています。そのためには、学生は、その分野の基礎知識だけでなく、最近の研究動向を把握する必要があります。学生がタスクをこなすだけでなく、「何を追求したいのか」という考えにじっくりと向き合う時間を設けることで、研究の喜びや自らの考えから導き出す喜びなどを伝えられるように心掛けています。
また、私の研究室には留学生や外国人研究者が所属しており、国際共同研究を進めています。自主研究の学生には彼らとのコミュニケーションを促進しており、こうした交流を通じて、英語でのディスカッション能力を向上させるだけでなく、異なる文化や視点を持つ海外研究者と交流することで、学生の国際的な視野を広げる機会を提供しています。また、学生が自由に興味のある分野の論文を見つけ、プレゼンテーションすることで、彼らの知的好奇心を刺激し、医学英語の基礎力を鍛える英語での論文抄読会も実施しています。異国で学ぶ留学生の中には、非常に高いモチベーションを持つ学生が多く見られます。こうした留学生との交流を通じて学生の学習や研究の意欲を高める取り組みを行っています。