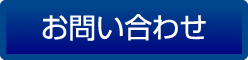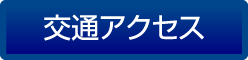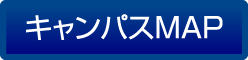ベストティーチャー賞(令和5年度)
ベストティーチャー賞
 |
氏名:佐藤 達雄 |
変革時代の授業を模索する ーベストティーチャー賞を受賞してー
この度、令和5年度鹿児島大学医学部医学科ベストティーチャー賞に選ばれたことを大変光栄に存じます。ご推薦頂いた皆さま、特に、私の試みを評価して下さったFD委員の先生方に、心より感謝申し上げます。
私が薬理学教室に着任したのは、コロナ規制が解除された令和4年度のことです。コロナ禍を経て、大学講義の在り方についての考え方が大きく変わり始めています。大講義室で知識を伝達する型の対面講義は本当に必要なのか?(Courseraなどの)専門家によるオンライン講義の方が教育効果が高いのではないか?といった問いが繰り返し提起されています。この問いに明確な答えを出すのは難しいですが、科目の内容や学生のニーズ、学部の教育方針、そして利用可能なリソースによって最適解は異なると考えています。こうした問いを常に自問し続ける姿勢こそが、これからの大学教育において重要であると感じています。
薬理学の講義を初めて担当するにあたり、まず私が振り返ったのは、自分が医学部で受けた薬理学講義のことでした。25年前、私が受けた薬理学講義は、化学に重きを置いたものと生理学に重きを置いたもの、様々なものがあったと記憶しています。薬理学は薬と生体の相互作用を解明する学問であり、化学と生理学の両方が不可欠です。これが薬理学が薬学部と医学部の両方で教えられている理由の一つとも言えるでしょう。
私たちの教室では、薬理学教育の目標を「病態生理学を通して薬物治療を理解すること」に設定しています。医学部2年生は薬理学講義までに既に生理学を履修しており、3年生では臨床科目でさまざまな薬物について学ぶことになります。薬理学講義では、これら生理学と臨床科目を橋渡しすることに重点を置き、化学的な内容は最小限に抑えています。講義は、まず疾患のケーススタディから始め、生理学を復習し、関連する薬物を学び、最後に薬物治療を考えるという構成です。この講義スタイルが薬学部などに最適かどうかは別として、医学部では非常に合理的であり、「医学部モデル・コア・カリキュラム」の垂直統合というコンセプトにも合致しています。
近年、教育効果をエビデンスに基づいて評価する「Evidence Based Education」の重要性が叫ばれています。どのような講義方針を取るにしても、それが正しいアウトプットに結びついているかを評価するシステムの構築が必要だと感じ、薬理学教室では試験形式を大幅に変更しました。答案は紙ではなくxlsファイルで提出させ、少しのプログラミングで120人分の解答を素早く自動採点してデータ化できるようにしました。理解度を確認するのは、理想的には長文記述にて行うのが望ましいのですが、採点の負担を考慮して穴埋め式の問題を採用しています。試験を二回行うことも、採点の自動化により(学生には不幸かもしれませんが)負担が軽減されています。実際、中間成績が悪かった学生が最終試験でも改善しない傾向を把握できるようになりました。今年度からは、これを踏まえてさらなる介入策を検討しています。今後、数年分のデータが蓄積されることで、より詳細な解析が可能になると考えています。
ある大学の薬学部では、生理学の「反転授業」が採用されています。学生が事前に講義ビデオを視聴し、講義時間内に演習を通して理解を深める形式です。アクティブラーニングの観点から学生の満足度は高いとされていますが、理解度に関しては従来の形式と大差がないという結果も出ています。私が感銘を受けたのは、この反転授業の先進性だけでなく、データに基づいて教育効果を評価している点です。私たちも教育を最適化するために、データに基づいたアプローチを見習いたいと考えています。
最後に、私が特に重視しているのは「一期一会性」です。対面講義の価値は何かと問われると、例えばoasis(再結成したばかりですが)のアルバムをダウンロードして聴くことと、地元のインディーズバンドのライブに行くことを比べるようなものだと感じます。oasisのアルバムは完成度が高くリスナーの満足度も高いですが、インディーズバンドのライブにはその場でしか味わえない高揚感があります(ここでは、oasisのライブのチケットは手に入らないという想定をしています)。対面講義の価値もまた、そうした躍動感にあると考えます。私の講義では、教室内を歩き回りながら学生に問いかけ、時には漫談のようなエピソードを交えてライブ感を大切にしています。
ベストティーチャー賞をいただいたことを励みに、現状に満足せず、今後も常に進化し続けていきたいと思っております。