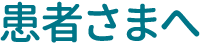Physical distancing:距離をとって繋がる
このところjet lagに悩まされている。国際Web会議のせいだ。当たり前だが、参加者は世界各国に居住しており、皆の時間帯を調整すると、少数派の日本人は平日深夜や早朝に割り当てられる。朝4時開始の会議にも、流石にパジャマ姿とはいかないし、ただでさえ不得意な英語が寝ぼけ頭で太刀打ちできるはずはなく、早めの起床となる。これが、9月頃から多いときは週に2回。身体はいつが昼か夜かわかっていない様だ。
さて、新型コロナウイルス感染症が流行し始めて以降、会議や講演は全てオンラインになり、移動時間を要さず、資料の共有も容易になった。反面、画面越しでのコミュニケーションは、直接の対面に比べると情報量は少なく、映像や音声の遅延もある。発言が重なるとタイミングを逸してしまい、発言しないままの人もいる。さらに、画面の表示人数には制限があるので、Web会議なのに表情や仕草での返答が充分には発揮できないことも多いだろう。
私も始めは苦労したのだが慣れると、まずは自分が会議の当事者であり、その場状況をコントロールしようとする能動的な姿勢が重要なのだと気づいた。視聴者ではなく、出演者であると。短い発言でもチャットでも、自分自身の姿勢や考え方を積極的に発言/発信すると信頼を獲得し、親しくなれるように思う。
新たな組織に参加した時には、気後れするのは当たり前だし、グループの価値観や流儀を学びつつ仲間になるのは時間がかかる。しかし、まずは意見を言ってみよう。黙っている人をオンライン会議で見る人はいない。まずは、自分がここに参加していることを他の参加者に確認してもらわなければならない。SNSの「つぶやき」は「炎上」になるが、Web会議上では、それが失敗に感じる発言でも議論になる。
米国には、国家が提供するメインカルチャーを検証し、それに対抗するカウンターカルチャーがある。例えば、大統領を称賛する人たちがいる一方で、大統領の不正を追及する映画を作ってしまうように、多様性を許容するのが米国だ。大統領選挙を1ヶ月後に控える中、N Engl J Medが新型コロナウイルス感染症に対する現政権の対応を批判する異例ともいえる総説を掲載した。「Dying in a Leadership Vacuum (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2029812) リーダーシップの空白により失われた命」。
これからのオンライン会議でも、多様な意見をもとに、新たな視点で物事を考えるようになるはずだ。
Webでほとほと疲れると、気分転換にスーパーへ買い物に出る。ここでも、2メートル以上のSocial distanceのかけ声が響く。しかし、この「Social Distance」という言葉、「密です」という発言、なぜか社会的な接触をも回避せよという呼びかけのような、人間同士の心理的な距離をとるような言葉に感じてしまう。友人や家族、周囲との関係が徐々に希薄になり、人間関係を社会的に断つ方向に感じてしまうのだ。
感染を恐れる余り孤立し過ぎては意味が無い。生命に関する危機とともに人間関係の危機が生じ、身体面だけでなく、精神面でも強いストレスだ。さらに、差別や偏見に進む可能性もある、どころか、現実に起こり始めている。
我々には、共感する力がある。ひとが苦しんでいたら、その立場になって相手を思いやる。困難で不利な条件でも、道を切り開く能力が備わっている。 遠方の家族と会うことすら制限される今。 自分にとって、家族や友人、周りで支えてくれる人達との繋がりが大切であることに改めて気付かされる。
必要なのは、「Social distance」ではなく、物理的な距離を保つ工夫をしながら、皆とコミュニケーションを続ける手段を駆使し、周囲とはしっかり繋がっていく「Physical distancing」なのだと自分自身に言い聞かせている。
鹿児島にもそろそろ寒気団がやってくる。寒い中でも、せめて心温かく、挨拶や言葉をかわしたい。
もちろん、マスクをつけて。